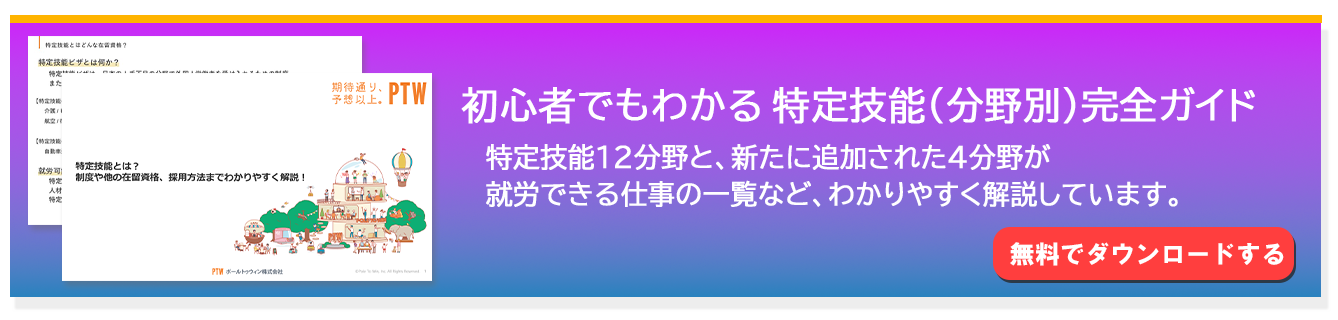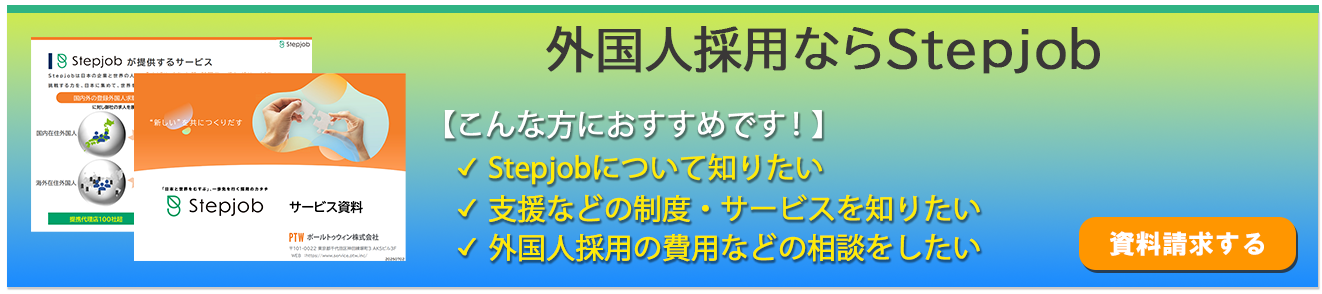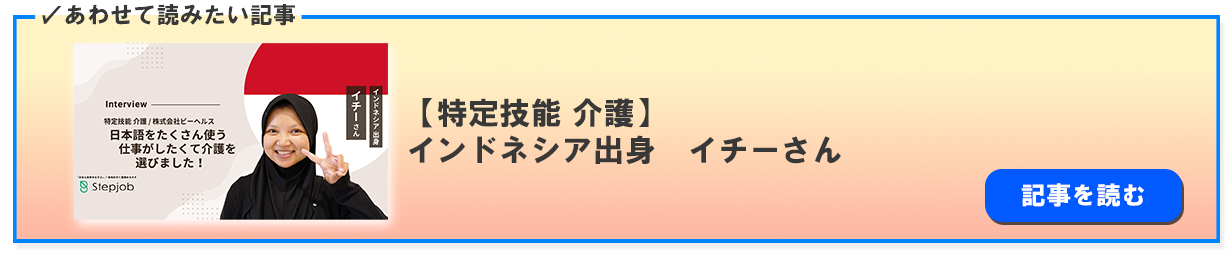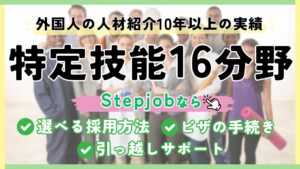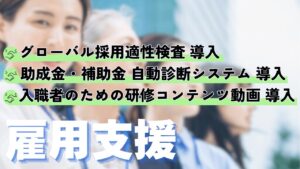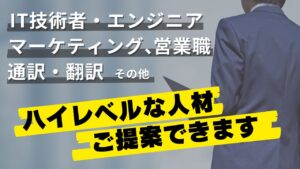日本の人手不足が深刻化する中、東南アジアから来日して働く外国人材の中でも、インドネシア人の存在感が高まっています。しかし、採用や職場でのコミュニケーションの場面で「宗教・文化の違い」に戸惑う企業も少なくありません。
日本の人手不足が深刻化する中、東南アジアから来日して働く外国人材の中でも、インドネシア人の存在感が高まっています。しかし、採用や職場でのコミュニケーションの場面で「宗教・文化の違い」に戸惑う企業も少なくありません。
この記事では、インドネシア人の性格・価値観・宗教文化をわかりやすく解説し、さらに企業が採用・定着を成功させるためのポイントを紹介します。インドネシア人材との上手な関わり方を知り、円滑な職場づくりに役立てましょう。
インドネシアとはどんな国?基本情報と社会背景

人口・民族・言語構成
インドネシアは東南アジアに位置し、2025年時点で人口約2億8,444万人です(日本貿易振興機関より)
また、国全体の平均年齢は29歳で比較的若く、日本と比べると約20歳も若いことが特徴です。
この若さが、国の活気と急速な経済成長の源泉となっています。
国土は約192万平方キロメートルで、日本のおよそ5倍の広さを持ち、1,300超の民族が混在しています。
公用語はインドネシア語ですが、多くの地方語・民族語も併存しています。
インドネシアの宗教的多様性
インドネシアは多宗教国家で、国民の約85%がイスラム教徒です。
それに続き、キリスト教、ヒンドゥー教、仏教の信者もいます。
国ではさまざまな宗教の自由が保証されているものの、無宗教は基本的に認められていないのが特徴です。
これは、特定の宗教を信仰していない人が多い日本とは大きく異なり、驚きをもって受け止められることもあるでしょう。
また、婚姻制度においても異なる宗教間の結婚は認められず、改宗が必要です。
多様な信仰への尊重と共生
インドネシアでは、イスラム教徒、キリスト教徒、仏教徒など、多様な宗教観を持つ人々が一緒に働いています。異なる宗教の信者同士でも、互いの信仰を尊重し合う文化が根付いています。
例えば、イスラム教徒は1日に5回祈りを捧げます。
これは仕事中にも祈りの時間が必要になることを意味しますが、多くのインドネシアの職場では、就業時間中にイスラム教徒が祈りの時間を取ることが一般的に認められています。
インドネシアにおける飲食事情
インドネシアは豚肉やお酒を避ける国というイメージがありますが、実際には個人の信仰や生活習慣によって異なります。
確かに、豚肉やお酒を扱わない店が多いですが、外国人が多く訪れる都市部のレストランではこれらがメニューにあることも珍しくありません。
一般的に多くのインドネシア人は豚肉やお酒を避ける傾向にありますが、イスラム教徒であってもこれらを摂取する人は存在します。
インドネシア人の性格・価値観の特徴
協調性と穏やかさを大切にする国民性
インドネシア人は「和」を重んじ、集団の調和を優先する傾向があります。
争いや対立を避け、周囲との関係を円滑に保つことを重視する文化的背景があります。
そのため、指示や意見を直接伝えるよりも、遠回しな表現を使ったり、空気を読みながら受け答えする場合がしばしば見られます。
仕事とプライベートの境界があいまい
インドネシア人の一部には、仕事とプライベートを明確に区切る意識が薄い傾向があります。
業務時間外に私用で抜けるなどの行動が理解されることもあります。企業はそのような可能性を念頭に置き、柔軟性を持った対応が必要でしょう。
また、定時内で働くことを重視し、残業を嫌う文化もあります。
残業を依頼する場合には、事前に納得感を持たせるコミュニケーションが重要です。
柔軟で順応性が高く、学習意欲も強い
インドネシア人は、新しい環境に順応する力が高く、指導を素直に受け入れる姿勢が特徴です。
日本での生活や職場のルールを積極的に学び、周囲に合わせようと努力する傾向があります。
<具体的な例>
- ・業務マニュアルを一度見ただけで自宅で復習するなど、自主的な学習姿勢を持つ人が多い
- ・挨拶や礼儀をすぐに実践するなど、文化的な順応も早い
- ・新しい機械やシステム操作も繰り返し練習して短期間で習得するケースが多い
また、インドネシアは「上下関係を重んじる文化」であり、上司や年長者に対して敬意をもって接する傾向があります。
そのため、指導に対して反発せず、感謝を示す姿勢を見せる人が多いのも特徴です。
一方で、あまりに厳しい叱責や強い言葉を使うと、黙ってしまう傾向もあるため、穏やかで丁寧なコミュニケーションを意識することで、よりスムーズな関係が築けます。
助け合い・相互扶助の精神(Gotong Royong)
インドネシアには「Gotong Royong(ゴトング・ロヨング)」という、相互扶助・助け合う精神があります。
チームで困ったことがあれば協力する態度が比較的強く、職場でその精神が現れることがあります。
この文化は、チームワークを重視する職場環境においてはポジティブに働く可能性があります。
インドネシアでゴトン・ロヨンの精神が行きわたっているのは以下の様な理由からです。
- ・周囲の人々との良好な関係を作る
- ・協力して問題を解決し一体感を生み出す
- ・協力する事で皆の安全と良好な環境を守る
- ・相互扶助の姿勢を育む
- ・結束を強める
- ・一人の負担を軽くして皆で支えあう
日本に対するインドネシア人の視点
好意的な印象
一般的に、インドネシアの人々は日本人に対して親しみやすく、肯定的な態度を示しています。
日本の車やバイクが広く使われており、アニメや漫画などの日本文化が大いに受け入れられていることから、日本はインドネシアにとって親近感の持てる存在となっています。
インドネシアが日本を歓迎する理由の一つとして、独立の父とされるスカルノやハッタが日本によって、オランダからの解放を受けたという歴史的な印象が強く残っています。しかし、現代の若者たちにとっては、このような歴史的な理由よりも、アニメやポップカルチャーによる日本への魅力が大きな影響を与えているようです。
「規律重視」のイメージ
多くのインドネシア人は日本を規律があり、清潔感のある国と認識しているようです。
また、日本人が勤勉で仕事に打ち込む国民性を持つという見解も共有されています。
ビジネスの面では、日本企業がインドネシアの仕事文化にどう適応するかが今後の課題となるでしょう。

日本企業との文化ギャップと注意点
納期・時間感覚の違い
インドネシア人は、ゆったりとしたペースと自由な時間感覚を持つ人が多く見受けられます。
このため、期限や納期に対する感覚が日本とは異なり、しばしば納期が後ろ倒しになったり、念押しをしないと忘れられがちです。
また、インドネシア人から具体的な期日を設定されることは稀で、期限を過ぎても罪悪感を感じることが少ないようです。
日本では時間厳守が常識ですが、インドネシアには柔軟な時間感覚を持つ人も少なくありません。
スケジュールに余裕を持つ・リマインドをこまめに入れる対策が有効です。
指示・フィードバックの伝え方
インドネシア人は基本的に穏やかでスローペースな性格の人が多いため、怒鳴られたり叱られたりする経験が少ない方が一般的です。
誰もが人前で注意されることに良い感情を抱くわけではありません。
インドネシア人を雇用し、注意する必要が生じた場合は、1対1の状況を作り別室で話をすることが適切です。
注意した理由と原因を明確にし、わかりやすい根拠を持って伝えることが求められます。
宗教的配慮の必要性
イスラム教徒の場合、礼拝(1日に5回)や断食期間(ラマダン)などの信仰行為があります。
礼拝時間を確保できる場所や、断食中の体調配慮、ハラール食の提供などがあると安心感を与えられます。
また、ジャカルタなどの都市部では、ジルバブ(またはヒジャブ)を着用する女性もいれば、着用しない女性も多く、その割合はほぼ半々です。
しかし、ジャカルタ以外の地域では、より敬虔な信者が多い傾向にあります。
ある人は「親は毎日ジルバブを着用するが、友人のほとんどが着用しないので私もしない」と言い、また別の人は「家を出るまでは親に言われてジルバブを着用するが、外に出たらすぐに外す」と話しています。
インドネシアでは宗教への取り組み方は人それぞれで、多様性が尊重される文化が根付いています。
企業ができる!インドネシア人材の採用・定着支援のポイント
明確なコミュニケーションと評価制度
インドネシア人は「人間関係」や「相手への敬意」を重視します。
そのため、感情的な叱責や曖昧な指示は混乱や不信感を招きやすい傾向があります。
職場では、以下のような工夫が効果的です
- ・口頭だけでなく、図や写真を交えたマニュアルを活用(視覚的に理解しやすい)
- ・できたことを積極的に褒める文化を取り入れる
- ・定期的な面談で、仕事ぶりを具体的にフィードバック
また、昇給や役職などの基準を明確にすることで、「努力すれば報われる」という安心感を与えられます。
こうした仕組みが、長期定着と職場への信頼感を高めるカギとなります。
キャリア支援とスキルアップの機会提供
インドネシア人は「家族のため」「成長のために働く」というモチベーションが強い傾向にあります。
そのため、スキルアップやキャリア形成の機会を用意することで、職場への定着率を大幅に高められます。
<具体的な例>
- ・日本語教育支援(N3→N2を目指すオンライン学習など)
- ・社内での資格取得支援(介護福祉士・調理師など)
- ・将来的にリーダー職へステップアップできるキャリアプランの提示
成長の道筋を明確に示すことで、「この職場で頑張りたい」という意欲を引き出せます。
さらに、定期的に目標を共有することで、企業と本人の間に一体感が生まれます。
宗教・生活習慣への配慮が定着率を上げる
イスラム教徒が多いインドネシア人にとって、宗教行事や食文化は生活の中心です。
職場で信頼関係を築くには、こうした文化的背景を尊重する姿勢が欠かせません。
<具体的な例>
- ・1日5回の礼拝時間を考慮し、勤務スケジュールを柔軟に組む
- ・ハラール対応の食事を持参できるよう、共用冷蔵庫・電子レンジを設置する
- ・ラマダン期間中は、断食に配慮して夜勤や軽作業へのシフト変更を検討する
といった小さな配慮が大きな安心感につながります。
宗教的行事を理解しようとする企業姿勢は、信頼や定着意欲を高める重要な要素です。
【入職者インタビュー】インドネシア人材の活躍例
インドネシア出身のイチーさん。特定技能介護として日本で働いています。
イチーさんは、「日本語をたくさん使う仕事がしたくて介護を選びました」と。
今後の目標は、「N2に合格して、介護福祉士の資格を取得することです」と語ってくれました。
よくある質問(FAQ)
Q1. インドネシア人は日本語レベルが高いですか?
→ 技能実習・特定技能いずれも、基礎的な日常会話レベルは習得済みな人が多いです。企業内での日本語教育サポートがあるとさらに円滑に。
Q2. 宗教行事や礼拝対応は必須?
→ 個人差があります。月1〜2回の行事や断食期間中は配慮があると好印象。
Q3. 離職リスクは?
→ 特定技能ビザや、技人国ビザの場合は転職が可能なので、日本人と同じように離職リスクはゼロではありません。離職リスクを減らすためには、定着率を上げることが重要です。キャリア支援とスキルアップの機会提供の他に、理解あるコミュニケーション・相談体制を設けることで大幅に離職率低下につなげることができます。
まとめ ― 理解と配慮が“信頼”を生む
インドネシア人材の採用・定着には、宗教や文化的背景への理解が欠かせません。
信頼関係を築くことで、長期的な活躍が期待できます。
Stepjobでは、外国人材採用に関する無料相談・マッチング支援を行っています。
【関連記事】
◎以下の記事では、インドネシア人を特定技能として採用する方法が解説されていますので、併せてご覧ください。
【特定技能】インドネシア人の採用ルートや注意点、費用などをまとめて解説|Jinzai Plus